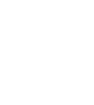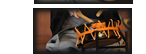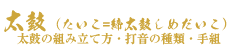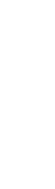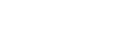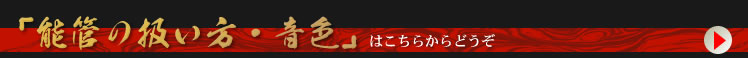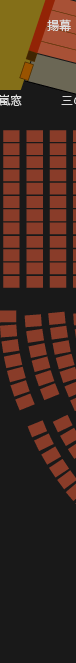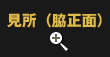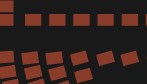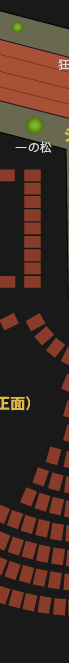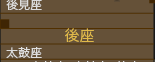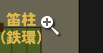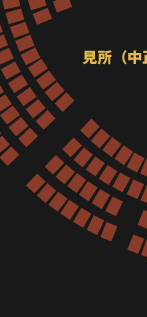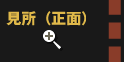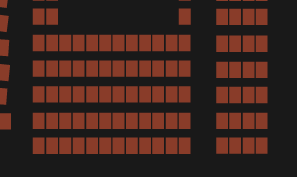能

能とは奈良時代に唐より伝来した雑芸のひとつ"散楽(さんがく)"から派生した日本固有の『舞謡劇』です。舞(まい)の舞踏的な動きに、謡(うたい)の声楽と、笛・小鼓・大鼓・太鼓による囃子(はやし)の器楽演奏が加わり、それぞれが渾然一体となり、物語が進行していきます。
“命には終りあり、能には果てあるべからず”(世阿弥 著『花鏡』奥段より)
能の大成者・世阿弥(1363年?-1443年?)が、数々の能楽論と作品を記してから六百年近く。その言葉通り、能はその様式を殆ど変えることなく連綿と継承されています。現在は、国内はもとより海外での演能も盛んに行われています。
能には、主人公であるシテをはじめ、シテの相手役となるワキ、六人から八人による謡を斉唱する地謡(じうたい)や、舞台の進行を補佐する後見(こうけん)など、様々な演者が登場します。
日本の伝統楽器の魅力を紹介する"THE和楽器"では、器楽部門にあたる囃子方にスポットを当てます。能で使われる楽器の奥深さや不思議な特徴を知って戴ければ、類稀なる伝統を誇る舞謡劇『能』の魅力がさらに深まること間違いありません。
 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
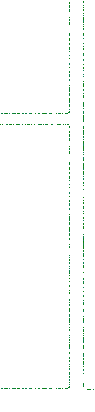 |
|
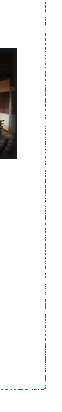 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||

能囃子の秘密
『マズ一サイノ事ニ、序・破・急アレバ、コレヲ定ムル事、コレワ、次第次第ナリ』
(世阿弥 著『花習内抜書』より)
能の囃子方は、舞台の舞謡を文字通り囃して(=栄して)ゆく器楽奏者です。同時に、舞台上に並んでいる通り、演者の一員であり、時にはシテという主役と対等に渡り合う存在となります。従って、見事な演奏を果たすことはもとより、その所作や姿に凛とした美しさが求められます。
能の囃子には指揮者はいません。しかも、そのリズムと間は一定ではなく、刻々と揺れ動きます。にも拘わらず、リハーサルのような通し稽古は一切行いません。あるのは簡単な申し合わせが一回のみ。そして一回きりの本番。各自が互いの表現を機敏に感知しながら阿吽の呼吸で一期一会の演奏を成し遂げなければなりません。此処に紹介する収録演奏も、すべて、ぶっつけ本番のワンテイクです。録り直しは一切ありません。独特の緊張感が漲る能の囃子をお楽しみください。


舞働(まいばたらき) 演奏時間 約1分20秒
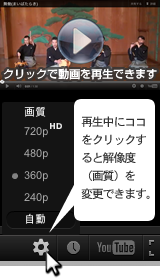

笛 森田流 笛方 松田 弘之(まつだひろゆき)
小鼓 大倉流 小鼓方 田邊 恭資 (たなべきょうすけ)
大鼓 高安流 大鼓方 安福 光雄(やすふくみつお)
太鼓 観世流 太鼓方 林 雄一郎(はやしゆういちろう)

脇能物(初番目物)においては、後シテである龍神・荒神・天狗などの力神が舞う力強さを凝縮した舞を舞働きという。四番目物・切能(五番目物)では、シテとワキとの戦いのさまを演ずるものが多い。神脇能の力強く豪快に演奏される「舞働き」はまさに一気呵成であり、船弁慶などでは鬼気迫る有り様を躍動的に表現している。

舞働が演奏される代表的な曲目
「賀茂」(かも)脇能物
別雷神(わけいかずちのかみ)(後シテ)が早笛(はやふえ)の囃子で颯爽と登場し、舞働きを力強く舞って五穀成就と国土守護を寿ぐ。
「竹生島」(ちくぶしま)脇能物
弁才天(後ツレ)が天女之舞を舞ったのちに湖上が鳴り、後シテの龍神が登場し、その勇ましい様を示して舞働きを舞う。
「船弁慶」(ふなべんけい)切能=五番目物
後場で見られる平知盛(たいらのとももり)の亡霊(後シテ)が、荒れ狂う海上で義経・弁慶一行に長刀を振りかざして襲いかかる。



羯鼓(かっこ) 演奏時間 約5分10秒
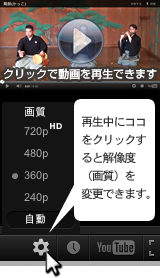

笛 森田流 笛方 松田 弘之(まつだひろゆき)
小鼓 大倉流 小鼓方 田邊 恭資 (たなべきょうすけ)
大鼓 高安流 大鼓方 安福 光雄(やすふくみつお)

腰に付けた小さな鼓(=羯鼓)を二本の撥で打って舞う軽やかな舞。中世に流行った大道芸を能に取り入れたもの。三段構成で、半ばで笛が羯鼓地(かっこじ)という羯鼓特有の譜を吹き、羯鼓を打つ様と軽やかな気分を表現する。羯鼓の囃子は太鼓の入らない、笛と小鼓・大鼓の大小の鼓とで演奏される。

羯鼓が演奏される代表的な曲目
「自然居士」(じねんこじ)四番目物/芸尽くし物
雲居寺(うんごじ)造営の寄付を募るため七日間の説法をしていた自然居士※が、亡き両親の追善供養のために我が身を売って求めた小袖を布施とした少女(子方)を助けるために、七日目の説法を途中で止め、人商人(ひとあきびと)(ワキ・ワキツレ)を追う。
追いついた自然居士は少女を返さないのならば、命を賭しても人買い船から下りないと迫る。困惑した人商人は居士をなぶるために様々な芸能を所望する。曲舞・簓摺(ささらすり)と続き、最後に羯鼓を舞って遂に少女を取り戻す。
※自然居士…庶民の中に入り説法をして歩いた実在の説教僧。
その他「花月」(かげつ)、「放下僧」(ほうかそう)など、四番目物の中でも芸尽くし物に多く見られる。



楽(がく) 演奏時間 約9分20秒
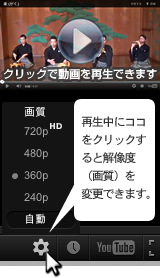

笛 森田流 笛方 松田 弘之(まつだひろゆき)
小鼓 大倉流 小鼓方 田邊 恭資 (たなべきょうすけ)
大鼓 高安流 大鼓方 安福 光雄(やすふくみつお)
太鼓 観世流 太鼓方 林 雄一郎(はやしゆういちろう)

中国から入った舞楽を能に取り入れるために、新たに作舞・作曲されたもの。ゆったりとした序から始まり、少しずつ速くなり後半はノリのよい位となる。変奏曲の構成で、進行して行くなかで移り変わる。多くが中国を舞台とした能に用いられる。
※通常は五段構成だが、今回の演奏では一部を省略した「三段楽」の構成となっている。

楽が演奏される代表的な曲目
「鶴亀」(つるかめ)脇能物
中国の玄宗皇帝(げんそうこうてい)(シテ)の元、四季の節会の初めの儀式が行われる。嘉例による鶴と亀(ツレ)の中之舞が舞われて皇帝の長寿が寿がれた後、皇帝自らが国土の繁栄を祝って「楽」を舞う。
「邯鄲」(かんたん)脇能物
中国、蜀(しょく)の国の廬生(ろせい)(シテ)という青年が人生に迷いを感じ、楚(そ)の国羊飛山(ようひさん)に住む聖僧に人生の大事を学ぶため旅に出た途中、邯鄲の里に着く。宿の女主人から"粟の飯の仕度の間に"と、借りた不思議な枕でうたた寝すると、楚の国王の勅使に起こされ廬生に皇帝の位を譲ると告げられる。廬生は王位に就き、それから五十年の栄華が続く。廬生はその栄耀栄華を「楽」に舞う。舞の途中で足を踏み外して目が覚めそうになるが舞続ける。そのさなか宿の女主人に粟の飯が煮えたと起こされる。目を覚ました廬生は全てが夢だったことに呆然とするが、人生は何事も夢と悟り故郷に帰って行く。



出演能楽師プロフィール

松田 弘之(まつだひろゆき)
森田流 笛方 1953年生まれ 国立音楽大学卒業
故 田中一次 並びに 故 森田光春に師事
東京を中心とした舞台活動を行う。語り・ダンスなど他のジャンルとの共演も多い。
公益社団法人能楽協会員 社団法人日本能楽会員 国立能楽堂養成課講師


田邊恭資(たなべきょうすけ)
大倉流 小鼓方 1980年生まれ
大倉源次郎に師事
国立能楽堂 第七期能楽(三役)研修修了
これまでに「猩々乱」「獅子」「道成寺」を披(ひら)く
公益社団法人能楽協会員


安福光雄(やすふくみつお)
高安流 大鼓方 1968年生まれ
故 安福春雄(人間国宝)及び父、安福建雄(人間国宝)に師事
10歳「羽衣」にて初舞台、13歳「鶴亀」にて初能以降、「石橋」「乱」「道成寺」「鷺」「卒都婆小町」を披(ひら)く。穿石会(せんせきかい)主宰
公益社団法人能楽協会員 能楽協会東京支部常議員 社団法人日本能楽会員
国立能楽堂養成課講師


林雄一郎(はやしゆういちろう)
観世流 太鼓方 1981年生まれ
観世元伯に師事。海外公演、新作能等にも幅広く出演。現在 東京を中心に活動中。
公益社団法人能楽協会員



四拍子~楽器の秘密

能の囃子を彩る楽器は、笛(能管)・小鼓・大鼓・太鼓(締太鼓)があり、これらを合わせて四拍子と云います。此処では、それぞれの楽器の不思議な成り立ちや基本な扱い方を御紹介致します。能の囃子方は、それぞれの楽器のみを演奏する専門職です。高度な技術を継承するため、ひとつの楽器に過酷な研鑽を積み重ねていかなければ成り立たない厳しい世界です。
ただし、私達アマチュアは、興味と熱意さえあれば、すべての楽器に挑戦することも可能です!!これを機会に是非、四拍子の道具に触れてみませんか?


能管(のうかん)

能楽囃子で使われる唯一の吹奏楽器。能の世界では、そのまま単に“笛(ふえ)”と呼ばれる。横笛でありながら、西洋音楽的なメロディを持たず、唱歌(※)を元にした節回しをリズミカルに力強く吹き鳴らす。能楽囃子においては打楽器的な役割も担う。



全長39センチ前後。管外径3センチ前後。笛材は竹。先端から歌口までの頭部分には節の太い真竹などの男竹が使われているものが多く、節の細い篠竹(女竹)と接がれている。指孔(ゆびあな)(写真右)は同一線上に七つ開けられている。



管の内外は生漆と砥粉などを混ぜた下地漆、朱漆が幾層にも塗り重ねられている。節と歌口、指孔以外の部分には樺桜の表皮を裁断して紐状に繋いだものや籐が巻かれ、その上からさらに黒漆が塗られている。指孔の間や歌口周りは竹の外皮は削られ、猫掻き、谷刳り(写真左)と呼ばれる技法が施されている。
頭部の裏側の爪形部分は、黒檀や紫檀などの別材が嵌めこまれている。昆虫の蝉を表した意匠であることから、この部分をセミ(写真右)と呼ぶ。


歌口の内部と頭部の間は蜜蝋で塗り固められている。頭の内部には笛全体のバランスを整えるために鉛錘が入れら、頭の先端には彫金した彫り物=頭金(かしらがね)(写真左)が嵌め込まれている。


上記の通り、堅牢に成形された耐久性に優れた笛であり、吹き込まれるほどに豊かな響きに変化を遂げていく。百年目からようやく本領を発揮すると云われおり、笛方が舞台で使う能管は三百年以上前に作られた古管(写真右)であることも珍しくはない。ただし、乾燥には弱いため、良いコンディションを保つためには継続的な息入れが不可欠である。


能管の歌口内部の蜜蝋(写真左)は、西欧楽器のフルートにおける頭部管内の反射板に該当する。その位置や分量の増減により、能管全体の鳴りやバランスを大きく左右する要となる。他の部分が固い材で堅牢に成形されているのに対して、この部分のみ柔軟性に富んだ材が使われている所以である。蜜蝋は経年の吹き込みによる劣化の際や、笛自体の響きの変化、笛方との相性に応じて、溶かして調整する。



小鼓(こつづみ)


柔軟な響きを持ち、自在に音色を変化させながら能楽囃子を色彩感豊かに彩る。表と裏の二枚の革の間に、中央がくびれた形に造られた胴(=鼓筒)を、調べ緒(しらべお)と呼ばれる麻紐で挟む形で組み上げる。左手で調べ緒に指を掛けて、右肩上に掲げ、右手で表革の打面を直接打ち上げる。

胴(=鼓筒)

胴は長年乾燥させた山桜の原木から、四十の工程を経て成形される。胴を作る鼓筒工(こどうこう)の家系は古くは室町時代まで遡るが、能楽が幕府の式楽に制定された徳川時代に隆盛を極める。

胴曲面に施された蒔絵(写真右)は蒔絵師による施しであり、鼓筒工による胴の制作と時期を同じくして成されれたものとは限らない。

 徳川時代の絢爛な蒔絵が施された胴(写真左)は、その時代からさらに数百年前に遡って作られたものであることも珍しくない。
胴の全長は約25~26センチ。重さは450±50グラム。その形は遠目では殆ど大差がないように見えるが、鼓筒工の家系によって作風が異なり、内部の削り、バランスをそれぞれの解釈で制作している。
徳川時代の絢爛な蒔絵が施された胴(写真左)は、その時代からさらに数百年前に遡って作られたものであることも珍しくない。
胴の全長は約25~26センチ。重さは450±50グラム。その形は遠目では殆ど大差がないように見えるが、鼓筒工の家系によって作風が異なり、内部の削り、バランスをそれぞれの解釈で制作している。



胴の内部には、カンナ目と呼ばれる刃痕(写真右)が残されており、元々は制作過程で付いた加工痕だったものが、職人の技巧を披露する意匠となり、作家性を残すための印に変性したのではないかと云われている。

革

革は馬皮。古くは当歳馬の鞍下の皮が使われた。直径は約20センチ。鋼の金輪に竹皮を巻き、その上に革を張り糸で縫い止め、長年の使用に耐えるよう漆が塗られている。打つ側の表革はやや厚く、裏革は僅かに薄い。

百五十年以上打ち込まれた状態の良い革は、老革(写真右)と呼ばれ珍重される。小鼓の革は、適度な湿気が必要なため、演奏する当日の天候や場の湿度に気を配らなければならない。

調べ緒

小鼓を組み上げるときに用いる麻の紐のことを調べ緒と云う。革や胴とは異なり消耗が早いが、この調べ緒も、鼓の音色を調整する際に重要な役目を果たしている。伸縮性と独特の腰の強さを持つ麻の特徴を最大限に発揮させるよう綯える(なえる)には熟練した職人の技が要求される。



大鼓(おおつづみ=大皮おおかわ)



外観は小鼓よりもひとまわり大きいが、突き抜けるような甲高い打音が特徴。大皮(おおかわ)とも云う。
表と裏の二枚の革の間に、中央がくびれた形に造られた胴(=鼓筒)を、調べ緒(しらべお)と呼ばれる麻紐で挟む形で組み上げられている点は小鼓と同じ。
ただし、小鼓の調べ緒は比較的緩く締められているのに対して、大鼓の調べ緒は極限まで締め上げられる。
左手で調べ緒を握り左膝上に載せた状態で、右手で表革をほぼ水平に打ち込む。

胴(=鼓筒)


※材や成形方法は小鼓の欄を参照。
胴の長さは28~29.5センチ。重さは750±50グラム。小鼓とフォルムは似ているが、胴の中央に鍔(つば)という飾り彫(写真右)がある。




小鼓の胴と同じく、いにしえの鼓筒工(こどうこう)が製作した胴内部には、カンナ目と呼ばれる刃痕(写真右)が残されている。


胴によって響きは異なるが、小鼓のように胴の寸法や内部の形状からおおよその音色の傾向を想定することが難しいと云われている。(写真左)

革


革は馬皮である点は小鼓と同じ。直径約23センチの極めて分厚く堅い皮(写真右)が使われており、革に漆は塗られていない。


大鼓の革は湿気が少しでも残っていると、澄み切った甲音は鳴らない。演奏前には、火鉢におこした炭火の熱で、二時間近くの時間をかけてゆっくりと焙じる。調べ緒を通した状態で専用の焙じ台に掛けて置く。(写真左)
過酷な扱いを繰り返すことになるため、革自体は十数回の使用で寿命を迎える。湿気を好み、百年以上使い続けることで本領が発揮される小鼓の革とはすべてが対照的である。

調べ緒

小鼓と同じく、大鼓を組み上げるときには麻の紐を綯えた(なえた)調べ緒を用いる。大鼓の胴に掛ける横の調べは、化粧しらべ(写真左)と呼び、その名の通り掛けておく装飾的な調べ緒で先端には飾り房が付いてる。



舞台に登場する際は胴に巻ている(写真左)が、演奏の際には解き、左脇に流し置く。(写真右)




太鼓(締太鼓)

演能において神や鬼などの超人的なものが登場する場面や、舞楽を盛り立てる際には欠くことの出来ない打楽器。能では、単に太鼓と呼ばれる。音の大小強弱関わらず、軽やかで柔らかみを帯びている打音を特徴とする。中央に緩やかな膨らみを持つ木製の胴を二枚の革で挟み、調べ緒(麻紐)で締め上げて、組み上げる。専用の台に掛けて床に据え、二本の撥(ばち)で打つ。

胴、撥(ばち)


胴は欅(けやき)や栴檀(せんだん)などの原木を刳り貫いて作られている。直径約30センチ、高さ約15センチ。胴外周部は蒔絵が施されているものも多い。(写真右)




胴内部には小鼓や大鼓の胴のように、鼓筒工独自の意匠のようなものは存在しない。ただし、平に削っているもの(写真左)以外にも、凹凸や刃痕を残している胴もある(写真右手前)。能で使うのは太桴(ばち)のみ。(写真右)撥材は檜が好まれる。

革



革は牛皮。表革中央の小さい円型部分は鹿の皮が貼り付けられており、“ばち皮”(写真右手前)と云う。ばち皮はその名の通り、桴を当てるポイントとなるが、革の保護よりも柔らかな音粒を出すための施しと云える。ばち皮の真裏にも“裏張り”(写真右)が貼られており、革の振動のバランスが図られている。革の直径は、約35センチ。小鼓の革のように縁周りの表面には黒漆、裏面には金箔押しが施されている。

調べ緒
小鼓と同じく、太鼓を組み上げるときには麻の紐を綯えた(なえた)調べ緒を用いる。

テレン台

締太鼓は二本の撥で演奏するため、専用の台に掛けて舞台床に直接置く。写真のような鈎先が緩やかに湾曲させた作りになっているものを、直線的で簡素な作りのブショウ台と区別するためにテレン台と云うが、能ではテレン台が大半のため、単に“台”と呼ぶ。高級な台は写真のような紫檀材が用いられる。



能舞台の秘密

現在のような能舞台が造られるようになったのは、室町時代末頃からと云われています。それ以前、世阿弥時代の能舞台といえば、演能のたびに寺社の境内や貴族の館の庭などに組み立てるような仮設の舞台が殆どでした。能が幕府の公式芸能=式楽に位置づけられた徳川時代には、江戸城だけでも複数の能舞台があったように、各地の城や自邸に能舞台を造る武将も多かったようです。
現在の能楽堂は室内に設置されているにも拘わらず、舞台の上に屋根が掛かっています。これは屋外に造られていた頃の名残なのですが、元々は遠くで観覧していた観客に舞台の音を効果的に届ける役割を果たしていました。その他、反響板としての効果も高い囃子座の後方の鏡板や、共鳴腔として本舞台の床下に据えられている大きな甕(かめ)など、音響的な創意工夫が様々に施されています。
また、一見すると簡素極まりない舞台空間もしかり。視覚的な演出や仕掛けは殆どなにもなく、客と舞台を隔てる幕さえもありません。この贅肉を削ぎ落した境地のような舞台だからこそ、演能が始まった途端に、観客に無限のイマジネーションを呼び起こすのです。聴覚・視覚すべてにおいて、高度に企てられた舞台装置が、能舞台なのです。


能舞台図


舞台図解説
鏡の間(かがみのま)
揚幕の奥にある板張りの部屋で、姿見の鏡が据えられていることから、こう呼ばれる。舞台に出る前の演者が、此処で面を掛け、精神を集中させる重要な場所。また、開幕を知らせる囃子方の“お調べ(=楽器の具合の確認を含めた音出し)”も鏡の間で行われる。
橋掛り(はしがかり)
後座から舞台に向かって左側に斜めに延びた長い廊下。単なる演者の入退場の通路ではなく、演技の重要な場となる。神・霊など超人的な存在が、異次元からこちら側の世界へと渡る象徴的な場でもある。橋掛り手前には三本の若松が配置されているが、装飾的な意味合い以外に、橋掛りでの演技の立ち位置の目安の役目も果たしている。
鏡板(かがみいた)
正面奥、後座の後方にある大きな羽目板。老松の絵が描かれている。小鼓や大鼓のように裏革が大きく共振する打楽器にとっては強力な反響板の役割を果たしている。
笛柱
舞台に向かって右手奥の柱。笛方の位置にもっとも近いので、こう呼ばれる。柱に取り付けられてる鐶(かん)=鉄環は、『道成寺』の作り物である鐘を吊るすために使う。
ワキ柱
舞台に向かって右手前の柱。ワキ(脇役)のいる場所=ワキ座にもっとも近いため、こう呼ばれる。
シテ柱
舞台に向かって左奥、橋掛りと交わる角にある柱。シテ(主役)は、この場所を起点にして演技を行うことから、こう呼ばれる。
目付柱(めつけばしら)
舞台に向かって左手前の柱。柱のなかでも特に重要。能は多くの場合、面をつけるため演者の視野は極端に制限されている。そこで、この柱に目を付けることで、舞台上の位置を見定めて舞うことから、こう呼ばれる。
切戸口(きりどぐち)
後座の向かって右奥、若竹が描かれた横羽目板にある出入り口。地謡方や後見が出入りする。斬られた役も此処から退くため、臆病口とも呼ばれる。
白洲(しらす)
かつて能舞台と観客席が別棟だった頃は、現在の見所場所には白い玉石が敷き詰められてた。自然の光を舞台に反射させる照明効果があったのではと云われている。その名残。
階(きざはし)
舞台の正面に掛っている三段の梯子。江戸時代には、階から寺社奉行が舞台に駆け上がり、演能開始の合図をしたと云われている。白洲に掛け降ろしているので、白洲梯子とも云う。現在は使わない。
見所(けんじょ)
観客席のこと。能が式楽だった頃は、この場所の大半は白洲が広がっており、客は後方の屋根の付いた桟敷から能を観覧していた。
※此処に掲載した能舞台の写真や、能囃子の録画は、東京・中野にある梅若能楽会館に御協力を戴いた。屋内の能楽堂では珍しく、自然光がたっぷりと射す能舞台である。撮影時も昼時であり、舞台の人工照明は最小限に抑えられている。
梅若能楽学院会館
財団法人 梅若会
https://umewaka.org/
〒164-0003 東京都中野区東中野 2-6-14 梅若能楽学院会館
電話:03-3363-7748 FAX:03-3363-7749